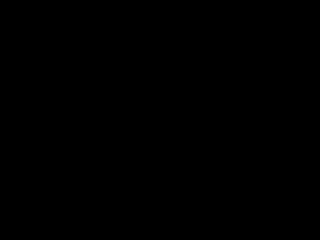背景
多くのマラソン大会の主催者にとって、電話対応は知られざる重労働です。
日本では、代表番号にかかってくる電話の多くが、
「エントリー方法を教えてください」
「雨の場合は開催されますか?」
「駐車場はありますか?」
など、毎年繰り返される同じ質問や、
協賛企業・業者からの営業電話、ボランティアからの確認連絡などが重なり、
運営チームが本来の業務に集中できなくなっています。
一方、海外のマラソン大会では、
「電話で受ける」ことそのものを見直し、
情報を共有・自動化・適切に振り分ける仕組みを整える動きが進んでいます。
事例①:ロンドンマラソン(英国)
TCSロンドンマラソンでは、公式のWhatsAppチャットボットを導入。
FAQデータベースと連携し、大会直前の1週間で
全問い合わせの85%以上を自動応答で解決しました。
緊急時や報道対応など、重要な問い合わせだけが人の担当者へ転送されます。
「スタッフが同じ質問への回答に追われなくなり、
ランナー体験の改善に時間を使えるようになりました。」
— ロンドンマラソン事務局 広報担当
成果: 電話応対の負荷を明確に分離し、繁忙期の運営がスムーズに。
出典: TCS London Marathon official WhatsApp service, Meta Business Case Study, 2023
事例②:ニューヨークシティマラソン(米国)
New York Road Runners(NYRR)は、問い合わせチャネルを2つに分離しました。
一般ランナー向け:公式アプリやWeb上のFAQ/チャットボット
報道・スポンサー・緊急対応:専用電話窓口
この運用により、電話件数は初年度で約65%減少。
ボランティアは現場サポートに集中でき、専門スタッフが重要な連絡を一元管理しています。
「すべての質問に電話は必要ありません。
それぞれに“最適な回答方法”を考えることが重要でした。」
— NYRR運営チーム
出典: NYRR Operations Insight, Marathon Handbook Report 2023
事例③:シドニーマラソン(オーストラリア)
シドニーマラソンではボランティア中心の運営体制を支えるため、
代表番号に音声AIシステムを導入。
かかってきた電話を自動で分類・振り分ける仕組みを構築しました。
主な特徴は:
リアルタイムで内容を分類(「エントリー」「天候」「医療」など)
多言語の音声を自動翻訳し、担当者へメール転送
応対内容の要約を自動生成して事務局と共有
その結果、対応時間を約60%短縮し、ボランティアの離脱率も減少しました。
「小さな工夫でも、パートタイムのチームにとっては大きな助けになります。」
— シドニーマラソン実行委員会
出典: Running Events Australia, Operations Brief 2024
学べるポイント
情報の一元化
FAQや過去の問い合わせ履歴を整理・共有し、誰でも対応できる環境を整備。電話は“最後の窓口”という発想
すべてを電話で受けるのではなく、チャット・メール・自動応答を活用。軽量な自動化ツールの活用
小規模大会でも導入できる、安価でシンプルなツールが増加中。効率化=人を減らすではなく、時間を取り戻すこと
自動化の目的は“人間らしい対応のための余白”を生むことです。
🧭 まとめ
世界のマラソン大会は、「人と人との接点」を減らしているのではなく、
より良い接点のつくり方を再設計しているのです。
すべての問い合わせを“人が受ける”時代から、
“チームで情報を管理し、最適な形で応答する”時代へ。
こうした仕組みは、
大会運営の持続可能性を高め、
ランナー・地域・スポンサーすべてにとって価値ある体験を生み出します。
参考資料
Meta Business Case Studies – TCS London Marathon WhatsApp Chatbot (2023)
https://www.whatsapp.com/business/success-stories/tcs-london-marathonMarathon Handbook – How the NYC Marathon Streamlined Runner Communication (2023)
https://marathonhandbook.comRunning Events Australia – Sydney Marathon Volunteer Operations Report (2024)
https://runningevents.com.auWorld Athletics – Marathon Operations and Communication Trends Report (2023 Edition)